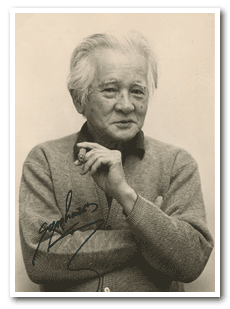 菅原明朗(本名・吉治郎)は1897(明治30)年3月20日、兵庫県明石に生れた。1913(大正2)年、兵庫県の柏原中学校(現・県立柏原高等学校)を経て京都府立第二中学校(現・府立鳥羽高等学校)に転校。府立二中では吹奏楽隊に入り、大阪の陸軍第四師団軍楽隊から派遣されてきていた小畠賢八郎らからフランス式のソルフェージュや管楽器の手ほどきを受けた。府立二中を終え、上京して川端画学校に入り、藤島武二のもとで油絵を学んでいたが、1915(大正4)年、中学校時代の友人、野村光一につれられ大田黒元雄を訪れ、大田黒を中心としたサロンに参加した。ここで堀内敬三、二見孝平らと知り合い、初めての作品「三つの音詩」(1915)を作曲した。大田黒が創刊した月刊誌「音楽と文学」の同人となったがこのサロンの中で明朗はドビュッシーなどのフランス音楽に強く引かれていった。また武井守成らが創刊したシンフォニア・マンドリーニ・オルケストラ(1923年からOST)に参加してマンドロンチェロ、アルチキタルラ、アイリッシュ・ハーブ等を演奏した。やがて堀内敬三から基礎的技法の不足を指摘されたことを契機として1919年から1925年まで奈良の上高畑に引きこもった。 菅原明朗(本名・吉治郎)は1897(明治30)年3月20日、兵庫県明石に生れた。1913(大正2)年、兵庫県の柏原中学校(現・県立柏原高等学校)を経て京都府立第二中学校(現・府立鳥羽高等学校)に転校。府立二中では吹奏楽隊に入り、大阪の陸軍第四師団軍楽隊から派遣されてきていた小畠賢八郎らからフランス式のソルフェージュや管楽器の手ほどきを受けた。府立二中を終え、上京して川端画学校に入り、藤島武二のもとで油絵を学んでいたが、1915(大正4)年、中学校時代の友人、野村光一につれられ大田黒元雄を訪れ、大田黒を中心としたサロンに参加した。ここで堀内敬三、二見孝平らと知り合い、初めての作品「三つの音詩」(1915)を作曲した。大田黒が創刊した月刊誌「音楽と文学」の同人となったがこのサロンの中で明朗はドビュッシーなどのフランス音楽に強く引かれていった。また武井守成らが創刊したシンフォニア・マンドリーニ・オルケストラ(1923年からOST)に参加してマンドロンチェロ、アルチキタルラ、アイリッシュ・ハーブ等を演奏した。やがて堀内敬三から基礎的技法の不足を指摘されたことを契機として1919年から1925年まで奈良の上高畑に引きこもった。奈良では、リムスキー・コルサコフ、ヴァンサン・ダンディ等の理論書を読んで翻訳し、マンドリンを中心とした楽器とその音楽の研究に没頭したが、楽器の特性を十分に把握したオーケストレーションの妙はこの時代に培われたものである。1922(大正11)年からは音楽生活に専念し、「Quasi Valse」、「真昼の行列」などの初期の代表的な作品を産み出すほか、バロックから古典派までの様々な曲をマンドリン合奏のために編曲し、同志社大学、OST等を指揮してプレクトラム合奏の技術向上にも大きな貢献を果した。特筆すべきことは、ドビュッシー、キューイ、サティ、プーランク、オーリック、オッネゲル、ミヨー、フェルー等のフランスの近・現代音楽やバルトーク、ストラヴィンスキーなどの音楽をプレクトラム合奏用に編曲し、OSTの演奏会を通して一般に紹介したことである。 1925(昭和元)年12月、武井に乞われて再び上京し作曲、編曲、指揮など多彩な音楽活動を再開した。1930(昭和5)年には帝国音楽学校作曲科主任教授に就任(1933年には解任)、新興作曲家連盟の旗揚げに参加(1933年には脱退)した。この時期、明朗に教えを受けた人々には、深井史郎、古関祐而、小倉朗、箕作秋吉、山本直忠、服部正ら、その後、作曲界で活躍した錚々たる人材がいる。1930年代は明朗の第一期黄金期であって、奈良時代に訳したリムスキー・コルサコフの『和声学要義』の翻訳書、『楽器図説』(その後『楽器図鑑』)、『管弦楽法 上・下』の相次ぐ刊行、「内燃機関」、「祭典物語」、「明石海峡」、「神仙調協奏曲」、「白鳳之歌」、永井荷風との交友から成立したオペラ「葛飾情話」、宮城道雄らと新日本音楽運動に参加している人々との交友と琴尺八などを使った一連の作品群、OSTや新交響楽団等などの指揮、「藤十郎の恋」等の映画音楽や放送音楽の作曲等など、様々な分野で意欲的に活躍した。 1938(昭和13)年の「葛飾情話」の作曲上演を契機として永井荷風と親交を深めていたが1945(昭和20)年には、荷風と共に戦災に遭い、明石、岡山に逃れる。岡山で「玉音放送」を聞き帰京するが、それから各地を転々とする厳しい生活の中で、キリスト教典礼、グレゴリオ聖歌、ラテン語を学び、およそ4年の歳月を費やして「聖譚楽 預言書」を書き上げた。また戦後の音楽教育の新訂に際して、全国各地の音楽教師のために開かれた講習会の講師として活躍する傍ら、リード音楽等の教育楽器を通した、新音楽教育の普及のために奔走した。 1963(昭和38)年の関西マンドリン合奏団の川口優和との出会いが再び明朗のマンドリン音楽への関心を呼び覚まし、その後も多くのマンドリン作品の作曲と編曲を残している。また1963(昭和38)年にはカトリックに改宗し、本格的な宗教曲が多いことも我国の作曲家としては異色である。1966(昭和41)年、70歳の頃、明朗は初めてのヨーロッパ旅行をした。この旅行は明朗に大きな影響を与え、ヨーロッパの文化や、古い建造物との出会いが、明朗の奈良時代の古い記憶を呼び覚ましたかのように『芸術新潮』誌上にイタリアの美術や奈良の仏教美術をテーマとした多くのエッセーを執筆し連載する。またヨーロッパ旅行は明朗の創作意欲にも新たな息吹を吹き込み、70歳から91歳での死に到るまでの作品の数は、それ以前の作品数を上回る。 1988(昭和63)年4月2日、カンタータ「ヨハネの黙示録」の作曲中に逝去。享年91歳。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||